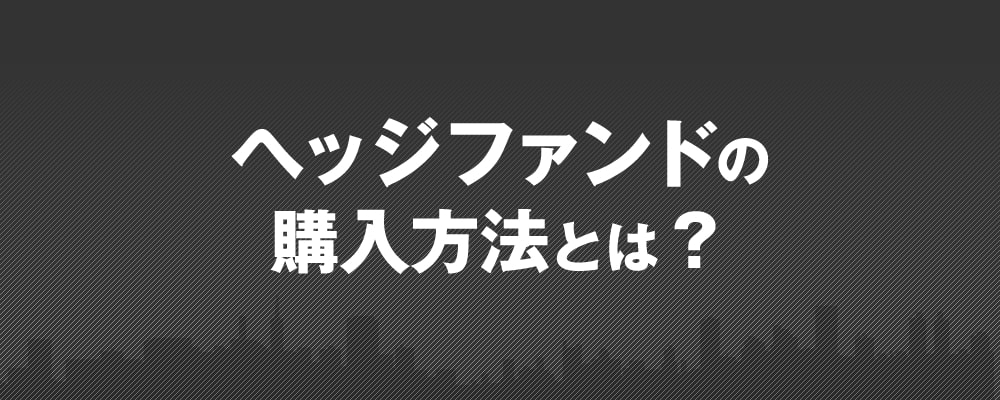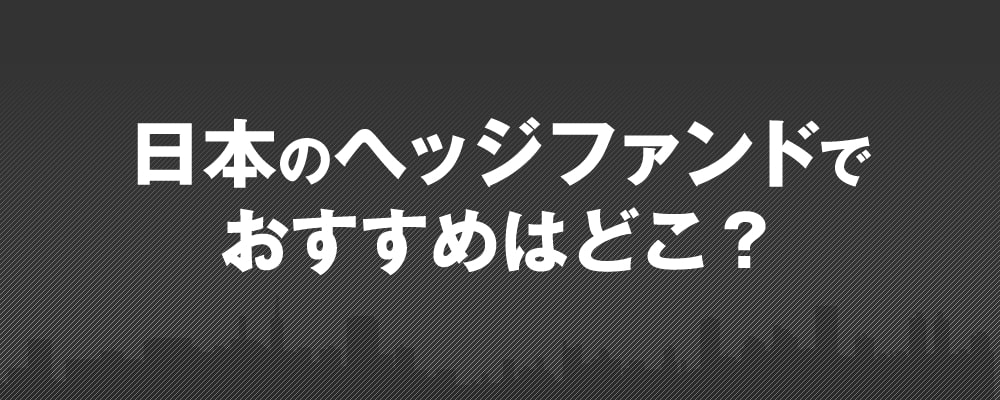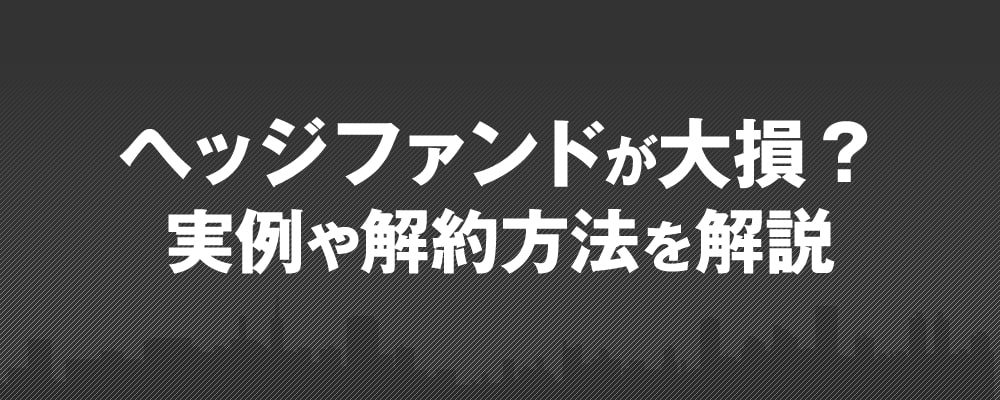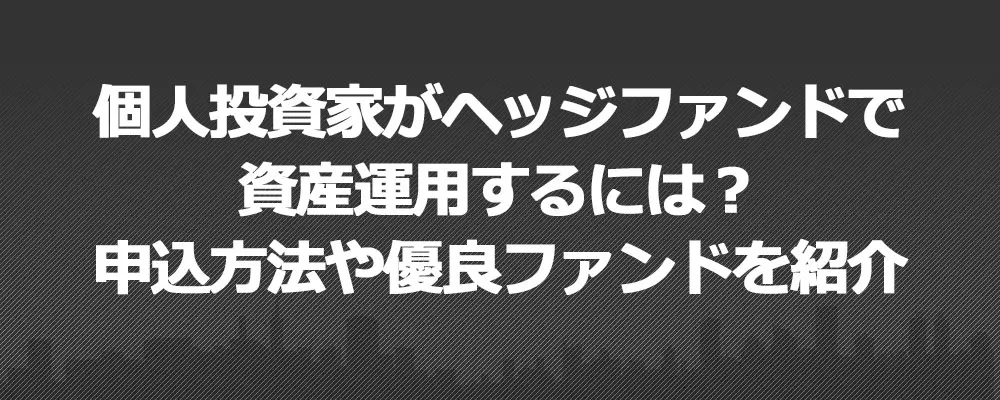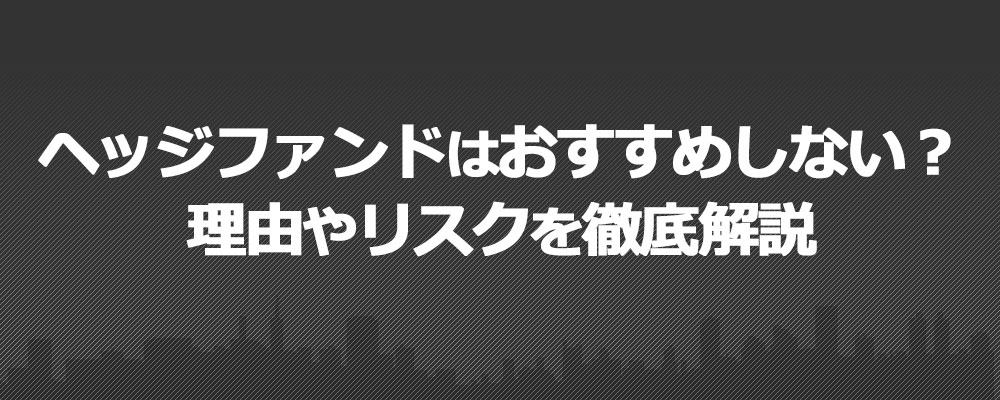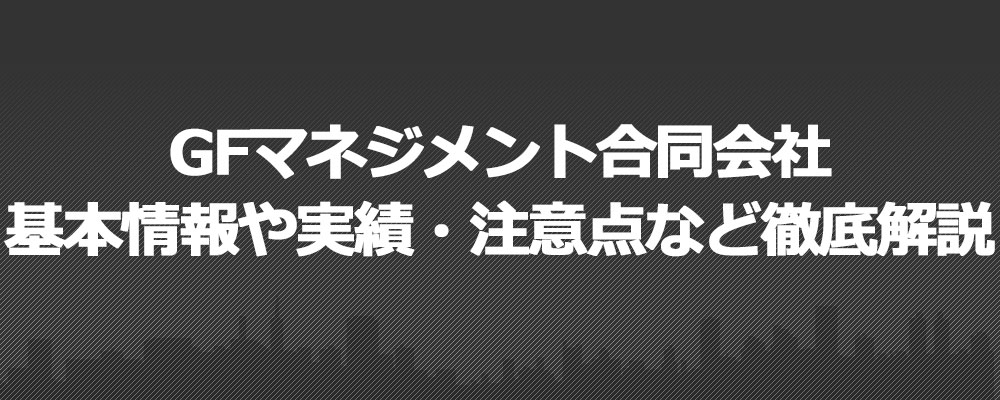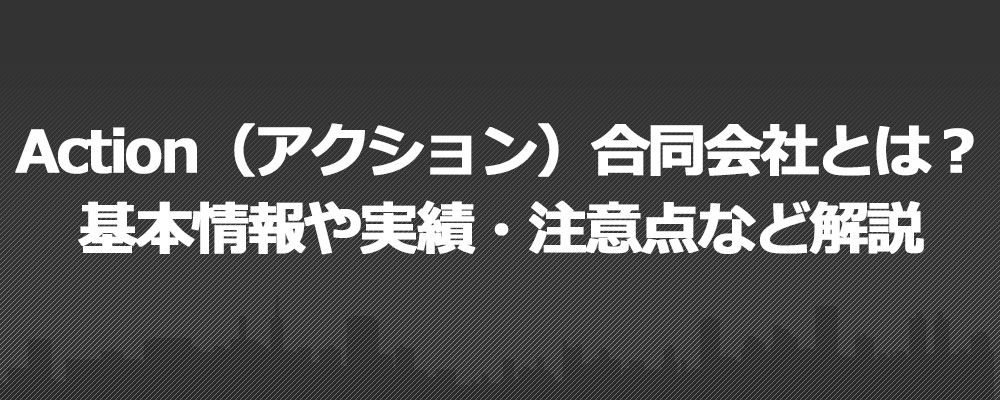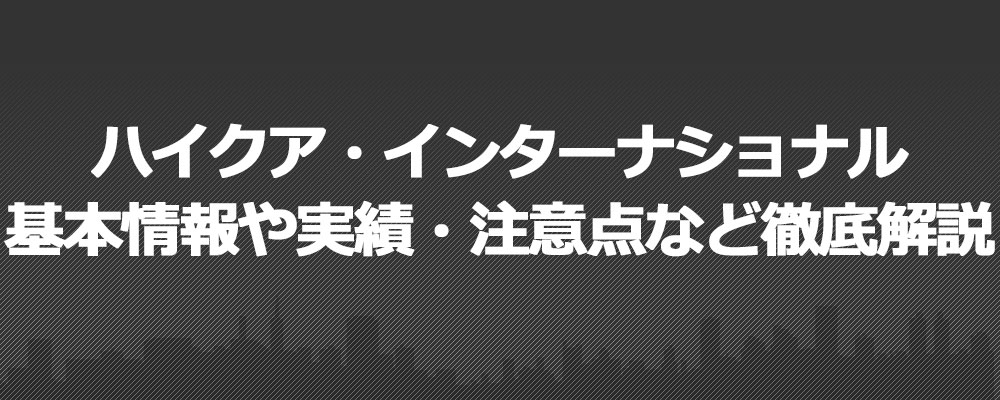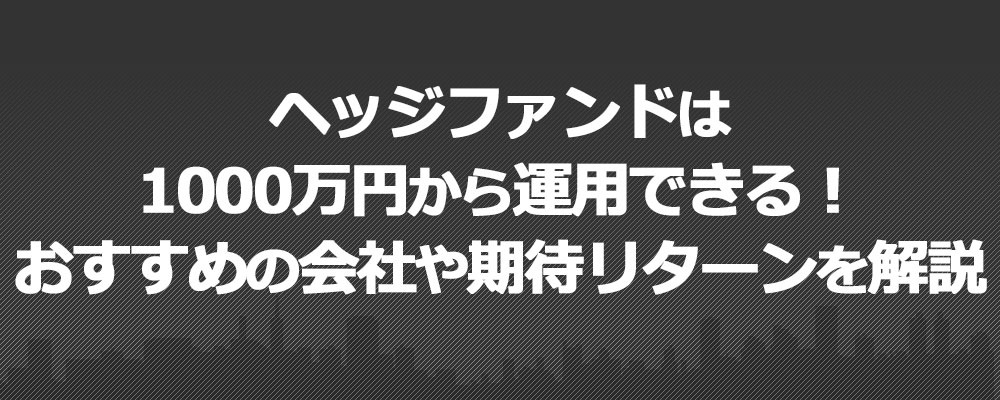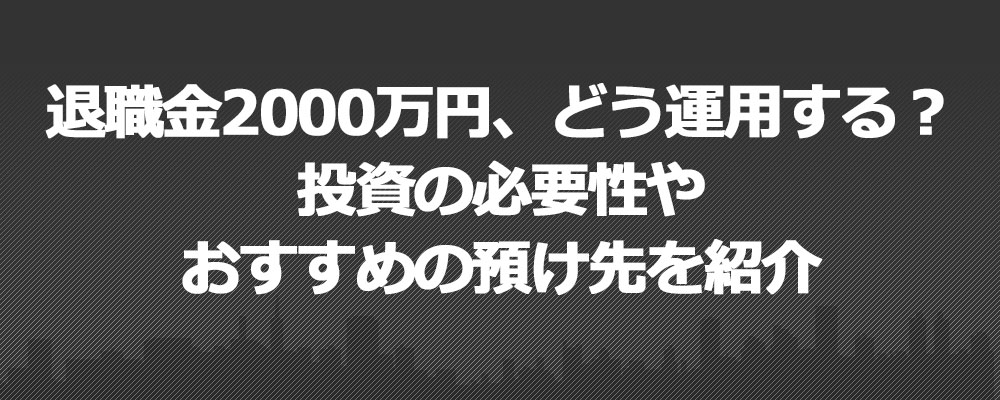ヘッジファンドへの投資は金融市場の相場状況によらず、高い利回りを狙うことができます。
しかしヘッジファンドは投資信託などに比べ、利回りが高い分、リスクも高いのが現状。
そこで考えるべきことは、ヘッジファンドにおけるリスクを理解することです。
本記事はヘッジファンドへの投資のリスクを徹底解説したうえで、リスク回避方法をご紹介します。
ヘッジファンドはハイリスクハイリターン
ヘッジファンドはリターン(利回り)が高い反面、リスク(損失の可能性)も高い、いわゆるハイリスクハイリターンの金融商品です。
ヘッジファンドと投資信託は混同されがちですが、運用方針や運用方法が大きく異なるので両者が抱えるリスクも異なります。
まずはヘッジファンドと投資信託についてそれぞれの特徴を説明していきます。
投資信託とヘッジファンドの大きな違いの一つに、運用の自由度があります。
投資信託は金融庁の管轄下にある金融商品ため、運用方法や運用資金などに厳しい規制があり、基本的にベンチマークを上回る運用を目指します。
ベンチマークとは投資対象の相場のことを指します。例えば日本株式に投資をしている場合は、日経平均株価などがベンチマークです。
投資信託ではベンチマークを上回っていれば良しとされているため、投資先の相場全体が下がり運用成績が落ちたとしてもベンチマークを超えた運用であれば評価に値します。
一方、金融庁の直接的な監視下にないヘッジファンドは比較的自由に資産を運用することができます。
ヘッジファンドによって運用方針や運用方法などの詳細は異なりますが、基本方針は「相場に関係なく常に利益を追求する」です。
ヘッジファンドは市場に左右されずに利益を出す運用を目指すので、投資信託と比較して利回りも高い傾向にあります。
資産運用で利益を重視するならば、投資信託よりもヘッジファンドの方が適しているといえるでしょう。
しかしヘッジファンドに投資するには、投資を始める前に理解しておくべきいくつかのリスクがあります。
では続いて、ヘッジファンドに投資するリスクを詳しくみていきましょう。
ヘッジファンドに投資する4つのリスク
ヘッジファンドに投資をすると下記4つのリスクが伴います。
では早速1つ目の、「元本割れするリスク」から解説します。
①元本割れするリスク
元本割れとは、投資した資金が運用の影響で投資した当初の資金を下回ることを意味します。
例えばヘッジファンドに1,000万円投資をしたが、運用が上手くいかず資金が800万円に減ってしまった場合、結果200万円の損失が発生して元本割れになります。
ただし元本割れのリスクはヘッジファンドに関わらず、資産運用をする上で覚悟する必要があります。
特にヘッジファンドはリスクを取った運用を行うため、投資信託に比べて元本割れする可能性は高くなるでしょう。
金融商品の中には元本が保証される、銀行の定期預金や国が発行する国債などの商品もありますが、これらの利回りは0.1%にも満たないので、元本が保証される反面、資金を増やす目的にはあまり適していません。
ヘッジファンドへの投資は元本が保証されていませんが、年間利回り20%や30%を超えるような高い利回りを追求できる面では魅力的ですよね。
また、ヘッジファンドへの投資は基本的に一定以上の期間の運用を想定しているので、月単位でマイナスの成績が出ても年間の利回りでみると利益が出ている場合もあります。
よってヘッジファンドを選ぶ際には一時的に見て元本割れしている時があったとしても、長期的な運用で利益を得ることができる商品なのかを見極めることが重要です。
②破綻するリスク
二つ目のリスクは、ヘッジファンドが破綻する可能性です。
過去に通称ドリームチームとも呼ばれたヘッジファンド「LTCM」がありました。
LTCMの運用陣はノーベル経済学者などの優秀なメンバーで形成され、運用初年度から高い成績を残したことから、世界中の投資家から大きな期待を寄せられていました。
しかし彼らは高パフォーマンスを追求して巨額のレバレッジ取引を試みた結果、取引に失敗し破綻にまで追い込まれました。
必ずしも実績のあるヘッジファンドが成功し続けるわけではないことがこの事例からもご理解頂けるでしょう。
投資先の運用の誤りによって会社が破綻し、最悪資金が1円も手元に残らない可能性があることは心に留めておくようにしましょう。
③詐欺のリスク
ヘッジファンドに投資をする三つ目のリスクは、詐欺の可能性です。
ヘッジファンドは運用方法や運用元が不透明な部分があるため、詐欺やポンジスキームの手法に利用されやすいです。
ヘッジファンドの中には「確実に利益が出る」や「利回り◯%以上の投資商品」などと言って集客することもあるようですが、これらは詐欺の可能性を疑った方が良いでしょう。
ヘッジファンドへの投資で高利回りや利益が保証されている商品はありません。
安全なヘッジファンドを見分けるには、運用成績などいい面だけを説明してくるヘッジファンドではなく、破綻や元本割れのリスクもしっかりと伝えてくるヘッジファンドを選ぶことをおすすめします。
④運営コストに関するリスク
ヘッジファンドでは資産をプロに預けて高いパフォーマンスを実現できる反面、諸手数料が他の投資商品よりも比較的高く設定されています。
ヘッジファンドの運用コストは主に「管理手数料」と「成功報酬」の2種類があります。
「管理手数料」は名前の通り、資産運用の管理にかかる費用(人件費や設備費など)です。
一方で「成功報酬」は運用で利益が出た際に報酬としてヘッジファンドに収める資金のことで、損失が出た際には一切支払う必要がありません。
「成功報酬」の額はヘッジファンドによって異なり、発生した利益の◯割と規定されています。
例えば、成功報酬が利益の30%の会社で1,000万円を1年間運用し、年間利回りが20%だったとします。
すると、運用資金は1,000万円×1.2%=1,200万円になります。
しかし運用で得た利益200万円の30%、60万円(200万円×0.3%)を成功報酬として収める必要があります。
つまり、最終的に運用資金は1,200万円−60万円=1,140万円になります。
運用で増えた資金が全て手元に還元されるわけではないので、手数料の事も加味してどの程度の期間、いくらの資金を運用するのかを考えるようにしましょう。
それでも冒頭でお伝えしたとおり、ヘッジファンドは相場状況によらず常にリターンを求める運用を行うため、手間やコストがかかる点を踏まえれば手数料が高い点は納得できますね。
では続いてヘッジファンドのリスク回避方法について解説します。
ヘッジファンドのリスク回避方法
ここからは具体的にヘッジファンドに投資する際のリスク回避いついて解説していきます。
ヘッジファンドはリスクが高いとはいえ、そのリスクを軽減することは十分可能です。ここでは以下の方法でリスクを軽減する方法を挙げてみました。
- 分散投資を行う
- 余剰資金で投資する
- 運用元のリスク管理を確認する
分散投資を行う
ヘッジファンドへの投資のリスク回避方法一つ目は、分散投資です。
分散投資とは、ヘッジファンドだけに投資するのではなく、他の金融商品にも投資をすることです。
投資対象を多数確保しておくことで、そのうちの1つの運用がうまくいかなくなっても他方でカバーすることができ、全体的に安定した運用をすることができます。
具体的には、全資産の大多数をヘッジファンドに投資するのではなく、現金や国債などの低リスク資産を一定数保有しておくことですね。
余剰資金で投資する
二つ目は、必ず余剰資金で行うことです。
「ヘッジファンドに投資するリスク」で記載したように、ヘッジファンドが破綻したor詐欺だった場合、投資資金が最悪0円になる可能性があります。
ヘッジファンドへの投資は元本が保証されないことを念頭に置き、投資は必ず余剰資金で始めることをおすすめします。
運用元のリスク管理を確認する
リスク回避方法の最後は、運用元のリスク管理を確認することです。
ヘッジファンドはリスク管理の方法についても会社によって様々です。
投資先のヘッジファンドが独自のリスク管理をしっかり行なっているのかを投資前の面談などで確認するようにしましょう。
リスク管理については下記のような項目に注目すると良いでしょう。
◯投資対象(投資対象が分散されているのか、投資対象が明確か等)
◯運用資金(資金管理がされているか、投資資金の運用割合はいくらか等)
◯運用実績(運用実績に偏りがないか、市場に大きく左右されていないか等)
特に投資対象がどのようなものかは事前に確認しておくべきでしょう。
ヘッジファンドといっても様々で、株式で運用するものもあれば、FXや先物取引などで運用するものもあります。
また運用の透明性についても把握しておくといいでしょう。
多くのヘッジファンドでは、運用対象やポートフォリオを公開していませんが、たとえば国内株式で運用していれば「大量保有報告書」などのレポートで運用実態を確認できます。
FXや先物取引では、このような運用実態の把握はできませんよね。
この点、当サイトおすすめヘッジファンド「BMキャピタル」は、日本株式で運用しており、大量保有報告書でも実態を確認可能です。
詳しくは以下のページにまとめていますので、BMキャピタルについて詳しく知りたい方はぜひチェックしてみてください。

まとめ
今回はヘッジファンドのリスクとリスク回避方法についてまとめました。
ヘッジファンドはリスクをしっかり理解して投資をすれば、高い利益を狙える優れた投資商品です。
今回ご紹介した4つのリスクを確認し、リスク回避方法を実践することで損失のリスクは幾らか軽減することができるので、ぜひ参考にしてください。
なお当サイトではヘッジファンドの購入方法を具体的にまとめている記事や日本のヘッジファンドランキングをまとめている記事もありますので、気になる方は是非チェックしてみてください。